|
● アルテッツァ 8SP仕様リアウーハの音質変更
20000129 更新
【動機・目的】
我が愛車アルテッツァはスーパーライブサウンド仕様だが、リアスピーカのウーハが出す音が
非常に気にくわない。
どこが気にくわないかというと、何ともモゴモゴした音で表現しづらいのだが、100〜400Hzぐらいのレベル
が強くて実に聞きづらいのだ。
いっそのことウーハを切った方が聞き易いのだが、低域の厚みが無くなる。
以前、●19990817 アルテッツァ 8SP仕様リアスピーカの調査
にてFFT解析を実施した。
線の傾きについてはあまり問題ないように見えるが、実際には聞きづらい。
純正のいいところを生かしつつ、自分好みの音にしたい。ということでウーハの特性を決めるLPFを、
こんな感じにしてみようと思う。

(これはイメージで、実際にこの特性で音が出ているわけではありませんので注意)
【調査】
○ 19990830 謎の別体式アンプの調査
スーパライブサウンドシステムは、フロントフルレンジ*2、フロントツイータ*2、
リアスコーカ*2、リアウーハ*2で8スピーカ構成となっている。
アンプはヘッドユニット内蔵式ではなく、グローブボックス奥に搭載されている。
このアンプで全てのスピーカをドライブする。(ナビ音声は別)
 このアンプを取り外す迄にものすごく苦労した。
このアンプを取り外す迄にものすごく苦労した。
アンプは、入力が前右、前左、後右、後左の4Chで、
出力が前右、前左、後右、後左、ウーハ右、ウーハ左の6Chである。
ウーハ系統には前後の入力信号にLPFをかけて出力する。また、大音量時はゲインを下げる。
○ 内部プリアンプから出力される信号
 右の黒い物体2本がハイブリッドIC 右の黒い物体2本がハイブリッドIC
このアンプには内部にプリアンプを搭載している。これは、ハイブリッドICとなっていて、小さな基板にOPアンプとチップ部品が実装されているような感じで、黒い樹脂でモールドされている。
基板のシルク印刷には、入力が前2Ch、後2Chで出力が前2Ch、後2Ch、ウーハ2Chであることがご丁寧に記されている。
ということは、このプリアンプでウーハへの信号を生成していることがわかる。
ひとまずこのアンプを車載状態で、ホワイトノイズを流し、特性測定を行った。
以下表は、ノートPCを車に持ち込み、プリアンプ出力をサウンド入力させたものである。
本ツールはWaveToolsというフリーウエアを用いた。
 左前プリアンプ出力 左前プリアンプ出力
 左後プリアンプ出力 左後プリアンプ出力
 左ウーハプリアンプ出力 左ウーハプリアンプ出力
パワーアンプからの出力もこれと同様とみてよい。
以上の結果からいえることは、ウーハ信号のみフィルタをかけていることだ。
耳障りなこもった音は、ウーハ特性の200Hz以上の帯域であろう。この帯域はリアスコーカでも十分再生できる領域である。
○ 机上視聴ならぬカーペット上視聴
 アンプをはだかんぼにして拝見。床上での視聴。 アンプをはだかんぼにして拝見。床上での視聴。
ウーハではない方の後スピーカの出力は全帯域出ているのかという疑問をお持ちのオーナーは
多いと思います。
特にスピーカのみ交換を考えているユーザはそう考えるのも無理ないと思います。
なにせこもった音のするウーハ、コンデンサが並列に入っているのではと思わせる位に
高域をぼかしたスコーカですから。
スコーカへの信号帯域は前スピーカ信号帯域と同様であることは、
前項の周波数特性で既にご理解頂いてると思います。
一応、室内に持ち込んでアンプを稼働させ、どんな音が出ているのか確認した。
1.条件
電源:ジャンクのスイッチング電源(スイッチング周波数:20KHz)
入力:ポータブルMD(ヘッドフォンジャックの出力を使用)
出力:密閉型の安物ヘッドフォン
2.聴感
| 出力 |
聴感 |
備考 |
| 前スピーカ |
基準 |
入力ショートしてもノイズ聞こえる。
(『サーー』っていうやつ) |
| 後スピーカ(スコーカ) |
前スピーカと変わらない。
少なくとも私の耳では判別不能。 |
同上。 |
| ウーハ |
例のコモリ低音がダイレクトに聞こえる。 |
同上。どうして? |
それにしても困ったのは、ノイズの多さ。
車だからまだ許されるものの、なんとかならないものか。少なくとも、室内で使えるレベルではない。
これでMD付きの6万高はいくら何でも高すぎない?
3.アンプ備考

・電源
市販の大出力パワーアンプには昇圧タイプの+−電源回路があるがコイツにはそれがない。
それらしいといえばデカい整流ダイオード1本と鉄心のチョークコイル1本が並列接続されているが
多分ノイズフィルタと思う。(違ってたらごめん)
別に昇圧タイプの+−電源回路が無いからといって悪いわけではない。
市販アンプはやれ何百ワットだの
っていうのがよく売っているが、多くのワット数を出力するためには、
ボイスコイルに多くの電流を流す必要があり、それには多くの電圧が必要だ。
一般的に、大出力のアンプというのは、小出力時の歪率が多いので小音量で聴くことが多い向き
にはかえって音質に不満が出るかも知れない。
アンプメーカは歪率のグラフをパンフに表示しているので自分のよく聴く音量と照らし合わせて
確認されたし。(店員素人多いですからね。)
脱線したがアルテッツァの音声出力としては、この電源方式は妥当といえる。
・電力増幅段のパワー素子について
オーディオパワーICを全部で3個使用している。型番までは拝見しなかったが、
前と後の分はパッケージが同じ大きさのため同一型を2個使用していると思われる。
ウーハはインピーダンスが違うせいか横幅が大きいICを専用に割り当てている。
動作方式は単一電源なので多分B級のBTLと思われる。無負荷時でもバイアスのため少しの発熱はある。
オーディオパワーICを使うと外付け部品は結構削減できるものだが、その割には多いのではという
感想を持った。
D級アンプなのではと思う位ケミコンがやたら多い。(ICからの出力にLPF噛んでないので違う)
・ハーネスについて
入力の信号線にはシールド線を用いていない。ただのリード線である。
自動車業界では常識のこの接続方式、オーディオに少し詳しい人から見ても非常識と思うだろう。
オーディーは以前、『ピリピリ』というノイズをクレーム修理して頂いたが、その原因はこのハーネスでは
ないかと思っている。
シールド線使って2〜300円高くても文句は言わないのだが。
○ 問題のLPF
先の特性から、ハイブリッドICからのウーハ出力が既にフィルタがかかっている状態であることから、
LPFはハイブリッドICの中に実装されている。このLPFをどうにかしたいところだが、ハイブリッドICのため、いじることは到底できない。
しょうがないので、ハイブリッドICのウーハ出力にもう1段フィルタをかけてやることにした。
つまり、"ハイブリッドIC出力"→"パワーアンプ"
を
"ハイブリッドIC出力"→"オーディー謹製LPF"→"パワーアンプ"
とする。
【改造】
○ 方式
まずは試作。ブレッドボード(写真右下の白いやつ)に回路をつくり、実動作を確認する。
 ブレッドボード上でLPF(ローパスフィルタ)の試作回路を組んだ。 ブレッドボード上でLPF(ローパスフィルタ)の試作回路を組んだ。
実際に聴いた上で、L(コイル)とC(コンデンサ)によるフィルタにオペアンプでゲインを得る方法が
一番単純で好みの重低音が出ることを確認した。
○ 回路について
 片Ch.分の回路 片Ch.分の回路
なんと鉄心入りのトランスとコンデンサ(C)を組み合わせてLPFを作っている。
当初CのみでLPF作ったが、ゲインを上げると高周波域まで聞こえてしまい好みの音が出ないし、
ゲインを下げると、低周波域が弱い。
そこでLとCを組み合わせたということだ。
トランスはインダクタとして用いているのだが、歪が大きいかも知れないが聴感上は問題ない。
コンデンサとオペアンプ(トランジスタ)でインダクタを表現できる。小型・低価格化できるので
Webご覧の人に改良をお任せする。
VR1は重低音調節用。
部品についてはどれも上等なものは使っていない。
両Ch作っても2000円超えないだろう。
 純正アンプへの接続 純正アンプへの接続
上記回路図のINとOUTはアンプのどこにつながっているかというと、左Ch.を例とすると、
INは、ハイブリッドICのWL.OUT端子に接続し、(下図参照)
OUTはカップリングコンデンサの+端子に接続する。
(当然カップリングコンデンサの+端子の足は浮かすことなる。)
 オーディー謹製LPF基板 オーディー謹製LPF基板
ブレッドボード上での試作・試験を終え、実際に蛇の目基板にパーツを配置した。
パーツに詳しい方はおおよその大きさがわかるだろう。
この大きさでも、アンプの中に仕込むことができるのだ。
○ ノイズ対策
そしてアンプ本体に銀紙でくるんだこのオーディー謹製LPF基板を仕込んで実車テストを行ったところ、
なんと、CDのスピンドルモータの駆動ノイズや、エンジン回転に動機したノイズがウーハに
低周波音として入ってくるではないか!
これではまずいと思い、このオーディー謹製LPFを別体式とした。
 オーディー謹製LPF基板別体式 オーディー謹製LPF基板別体式
信号の接続線はもちろんシールド線である。謹製基板も絶縁した銀紙で包む。
 これで再度実車試験に臨む これで再度実車試験に臨む
○ 設置
信号の接続線はもちろんシールド線である。謹製基板も絶縁した銀紙で包む。
設置場所は、グローブボックスのヒンジ裏。ビニールテープで固定した。
【改造後の性能】
○ 内部信号のFFT解析結果
改造アンプの内部信号の特性はどう変化しただろうか?
 ハイブリッドICからのウーハ出力 ハイブリッドICからのウーハ出力
 オーディー謹製LPFからの出力 オーディー謹製LPFからの出力
ノーマル状態(上段)では、100Hzから上は少しずつゲインが下がるのに対し、
オーディ謹製LPF(下段)は20〜30Hzが少し増えて、100Hzより上はレベルの下がり方が急峻である。
これは、LPFをLCで構成していることによる効果で、オーディーが所望しているスーパーウーハ的な特性である。
これでアルテッツァのウーハは、聞き苦しい高音を出さずに済むだろう。
○ リアスピーカ(ウーハ、スコーカ共の)FFT解析結果
改造前
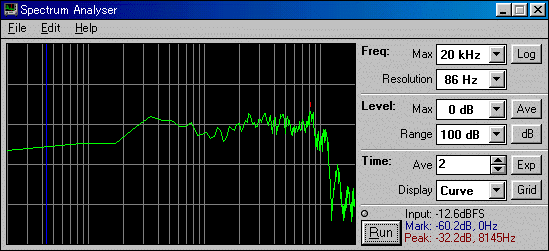
改造後

改造後は全体的にレベルが下がっているが、これは改造前とボリュームの位置が違っているためである。
20〜100Hzは改造前よりレベルが上がり、200Hz付近は改造前より落ちている。
○ 聴感
モゴモゴ音が消え、不快感は無くなった。
ノーマルより20〜100Hzが強調されたため、重低音が力強く聞こえ、結果的にはほぼ満足いくものとなった。
がしかし、これは前席で聞いた場合の話で、後席で聞いたときは『まずいかな?』と思ってしまった。
モゴモゴ音がまだ残っているのである。
もう少しカット周波数を低めに設定する必要があるだろう。
それから、CDプレーヤのサーボモータが動くたびに、直流成分に近いノイズが若干乗る。
走行中はロードノイズなどで全く分からないが、エンジンを止めると聞こえてくる。
上記のノイズ対策では不十分だったようだ。
【改善の余地】
素人の工作が故に、まだまだ改善の余地がある。
1.ウーハの高域カット周波数をもう少し下に設定する。
2.ノイズ対策
3.トランスを廃止
トランスの代わりに、オペアンプ+CでLを表現する方が安上がり。
4.ウーハ調整つまみ
ウーハの効きをボリューム調整出来るようにする。
|

